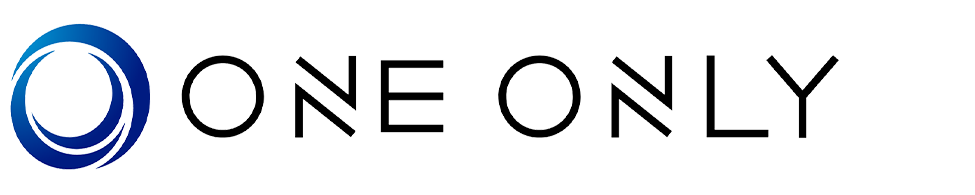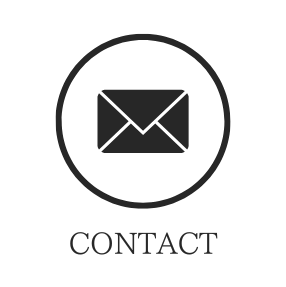ブログ BLOG
こんにちは、ワンオンリーです。
全国の工務店さんを日々サポートしている中で、最近とくに感じていることがあります。
それは――
「少人数の工務店さんこそ、お客さんにとってめちゃくちゃ価値のある存在だ」**ということ。
「うちは小さいから…」と謙遜する声をよく聞きますが、実はその“小ささ”が今、強みになってきているんです。
今日はその理由を、「パッシブ設計」と「デザイン住宅」の切り口からお伝えします。
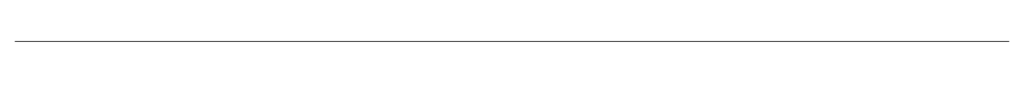
■ パッシブ設計って、難しく聞こえるけど実は“当たり前のこと”なんです
「パッシブ設計」って言葉、ちょっとカタいですよね。
でもやってることは意外とシンプルで、
・冬は日が入るように窓を設ける
・夏は日差しを遮る工夫をする
・風が通る間取りにする
要するに、自然の力を上手く使って、快適に暮らせるように設計するってことです。
これ、昔から家づくりやってる工務店さんなら、感覚的にわかってることが多いと思うんです。
「冬にあったかくて、夏は涼しい家にしたい」なんて、当たり前の感覚ですもんね。
でも、それを“設計としてちゃんと理屈立てて伝える”ことで、お客さんからの信頼がグッと上がるんです。
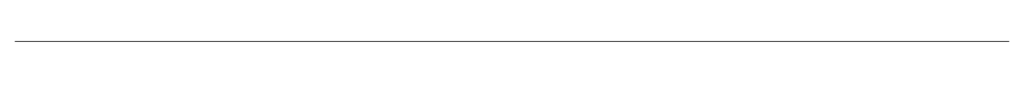
■ 少人数工務店だからできる「暮らしに寄り添った設計」
ここが本題です。
大手ハウスメーカーと違って、地域の少人数工務店さんは、お施主さんと密に関わるからこそ、こんな強みがあります。
・家族の暮らし方に合わせた提案ができる
・敷地の特徴を読み取って設計できる
・現場と設計が分断されてないからブレない
つまり、お客さんにとっては、**「ちゃんと話を聞いてくれて、それを図面にしてくれる人」**なんですよね。
これはもう、少人数だからこそできる価値提供。
外注や分業じゃなく、**自分たちの手でつくるからこそ伝わる“安心感”**があるんです。
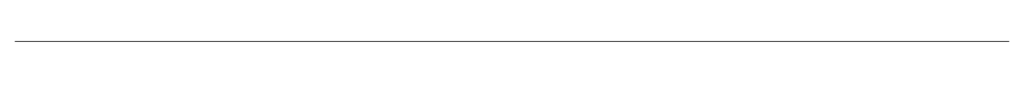
■ パッシブ+デザイン=選ばれる理由
最近は「性能がいいだけじゃなくて、おしゃれな家に住みたい」っていうニーズが増えてます。
でも、これって別々の話じゃなくて、パッシブ設計とデザインって、実はめちゃくちゃ相性がいいんです。
たとえば──
・軒の出を深くすると、夏は涼しく・見た目も重厚感が出る
・窓の配置を考えると、風通しもいいし、外観も整う
・土地に合わせた間取りにすると、自然とオンリーワンのデザインになる
つまり、「暮らしやすい」と「かっこいい」は両立できるということ。
それを叶えられるのも、地域で顔が見える少人数の工務店だからこそです。
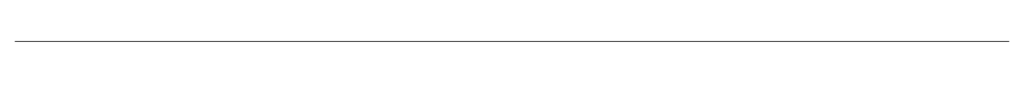
■ お施主さんが「選ぶ基準」は変わってきてる
最後にちょっとだけマーケティング視点の話も。
最近、家を建てる人の「工務店選び」の基準が変わってきています。
昔は「有名かどうか」とか「展示場があるか」が重視されていました。
でも今は、
自分たちの話をちゃんと聞いてくれるか
デザインや暮らし方を一緒に考えてくれるか
自分たちに合った家をつくってくれるか
こういう“フィーリング”や“共感”がすごく重視されているんです。
つまり、工務店のサイズじゃなく、どんな提案ができるか・どんな関係が築けるかの時代なんです。
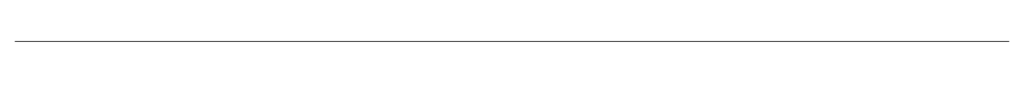
■ まとめ|「少人数」こそ、これからの家づくりのスタンダードかも?
少人数工務店の皆さんが普段やっていること。
それって、これからのお施主さんに求められてることそのものなんです。
暮らしに合った提案ができる
丁寧に設計・施工できる
寄り添う関係性が築ける
それを「ちゃんと伝える」ことで、もっと多くの方に届くはずです。
🔍 編集後記|「うちの強み、どう発信する?」そんなときはご相談ください
私たちは、住宅業界に特化したマーケティングや戦略支援を行っています。
「うちは設計力があるけど、うまく伝えられてないかも…」
「ブログとかSNSの発信、何を書いていいか迷ってる…」
そんなときは、強みを整理して、言語化するところから一緒にやってます。 気軽にご相談くださいね。
情報のリテラシー
週刊誌やテレビで話題になるとすぐにSNSで拡散されていきますが、そのほとんどが「炎上」なる悪い情報の拡散であることが多いようです。
最近では、お笑い芸人の過去の出来事に対して多くの誹謗中傷やスポンサーに対しての抗議など、問題が起こってしまうとなかなか収束は難しいようですね。
情報が広がりすぎると、様々な憶測やデマも混じりカオスな状況を作り出すこともあります。私たちのような、情報を受け取る側にも情報選択とリテラシーが求められると強く感じます。
そんな中で最近よく感じるのは、私たちは目の前の出来事に対して、自分の管見の範囲でしか判断できていなのではないか?
自分の目に見えている部分だけで物事を判断してしまっているんじゃないか? という点です。
酔っ払いの自転車乗り
有名は話で、酔っぱらいの自転車乗りという話があります。
ひと昔前に自転車に乗った酔っぱらいが、店から帰宅する道中に家の鍵を落としてしまいます。鍵が落ちたことに気づいた酔っぱらいは、慌てて自転車を止めて鍵を落とした場所を探してみます。しかし辺りは暗く、街灯がある場所しかよく見えません。
酔っぱらいは必至に街頭の下を延々と探しますがなかなか見つからない。
それもそのはず、鍵は街頭の下ではなく街頭の当たらない真っ暗な場所に落ちていた。
という話です。鍵が落ちた場所を探すのではなく、自分が見えている場所だけを探している。
これは選択バイアスの一つですね。 見えるところしか探せないので、その場所にあると思い込み(バイアス)が働いて
もうひとつ、戦闘機の補強の話があります。
戦時中に数多くの戦闘機が出撃していきます。それらの戦闘機が敵から銃撃を受けて一部が破損していきます。しばらくすると、破損を受ける箇所がおおよそ同じ場所だということが判明します。ならばと、破損する回数が多い箇所を補強します。
しかし、そこは戦闘機にとっては重要な箇所ではなく、もっと他に銃撃を受けるとひとたまりもない心臓部の補強が必要なのに、、、、。
これも銃撃を多く受けている部分に意識が働き、選択バイアスがかかっているといえますね。
知識や認識
私は最近、家族とアニメのNARUTOをよく見ます。
主人公のライバルの兄(うちはイタチ)が写輪眼という、様々なことを見通す力をもっているのですが、そのイタチも言っていました。
「知識や認識とは曖昧なものだ。その現実は幻かもしれない。人はみな思い込みの中で生きている、そうは考えられないか?」
深いですね。
これも選択バイアスに縛られるなという警鐘なのではないかと。
自分の持っている情報、知識、経験、これらだけで判断してはいけない事が数多くあると 改めて実感した4月でした。
ワンオンリーの指針にパレット経営というものがあります。
これは、特に人に対してや物事の捉え方に対して絵画のパレットのように様々な場所に様々な色を
入れることができて、 大きいパレットではその色が混ざり合うことで全く別の色に変わる。
事業も人も、多様性を大切にして真っ白なパレットのように受け入れる姿勢を大切にしているという
会社の考え方です。
そんなワンオンリーのメンバーは、確かに多種多様な人材が集まっています。
オープンマインドでチャレンジ精神があり、物事を楽しむ力が強い。
その反面、慎重さに欠ける部分がある。 そんな共通ポイントがあります。
13の指針
ワンオンリーの13の指針の一つに「人材に対して、まずありのままを受け入れる。それが信頼の証」という言葉があります。
人は相手によって態度や性格が変わることがあります。 または、気分や自身の状況によっても変わることがあると思います。
余裕がない時に関係のない話を持ち出されてイライラしたという経験はありませんか?
人は24時間365日を平静で居ることは難しいものです。
そうなると、「どの時」が本当の自分なのか。。。。
一度は考えたことがある人もいるのではないでしょうか?
また「その時々」によって相手からの見え方や評価も変わるものです。
いつもは元気で話しやすい方も、余裕がない時にせっかちで少しイライラしているように見える。
いつも元気な部分しか見えていない人と 少しイライラしている時しか見えていない人
見え方は180度変わってしまいますね。
人の本質
昔何かの本で、人は社会性の生き物なので「自分がどう思っているか」よりも「どう思われているか」の方が重要だと書かれていたことを思い出します。
「自分ができない」と思っていて周りに「出来ない」と思われることよりも、
「自分ができる」と思っていて周りに「出来ない」と思われることの方が、不幸せだと。そのような内容だったと思います。
確かに自分の評価と周りの評価にギャップが大きいと、社会性の生き物なので不幸せなのかもしれません。
ただし、そんな自分も含めて自分自身だと強い芯を持てれば、何の問題もないことです。
信頼するということは、その人の良い部分も悪い部分もひっくるめて人間として存在を認めることだと思います。
- 納得いかない時は、みるみる表情が強ばり頑として認めない意思
- 過去の出来事の記憶が曖昧で、記憶の引き出しに蓋をしている頭
- 理由はないけど、とにかく自信だけはある
- 何があるかわからないけど、とにかく飛び込んでみる
すごく良いことだと思います!
そんな素晴らしい才能が様々な色に変化し、またシナジーが生まれ新しい色に変化し続けられるよう、たくさんのパレットを準備する努力をしていきたいです。

日常の会話でも何気なく飛び交うブランディングという言葉。
ブランディングの効果はどこに発揮されるのか
- 自社の良さを理解してもらうためのブランディングが必要なんだ
- ブランディングがないと売れない
- いまはブランディングに力を入れるべきた でも「ブランディング」という定義がバラバラだと、共通言語のはずのブランディングが全然違う解釈になってしまいます。
ブランディング=認知拡大?
そもそも 「ブランディング=認知拡大」 と解釈とされる方も多いように思います。
ブランディングの定義を調べてみると、 「ブランディングは、ブランドの価値を高め、顧客や取引先と社会全体に、自社と自社の商品やサービスを「独自のもの」として認識してもらい、他社と差別化を図る取組です。」 ブランド認知というよりは、独自性のあるものを形成できている状態。という解釈になると思います。
私たちもブランディングについて考える際には、まず定義を考えます。
その定義は、 「A=B、B=Aの両方が成り立つ。また、それを第三者が認知している状態」としています。
自分たちだけが認知している状態ではなく、あくまで第三者によって認知されているか否か。
これって当たり前ですがすごく重要です。
伝えたい自社のつきつめた思い
「伝えるよりも伝わるかどうか」 「どう思っているかよりもどう思っていると思われるか」 なんだか一休さんのトンチのような話になってきましたが、ここがアウターブランディングのブランド形成が多い所以なのでしょうか。
ただ反対に 「伝わるかどうかは、どう伝えたいかがあるから伝わる」 「どう思われるかは、どう思っているかをつきつめているから伝わる」 ともいえます。
結局のところ、 「どう魅せるか」を考えたときには、「どう魅せたいかをつきつめて考える」しかないのかもしれません。
脂っこく表現される 「自社の思いが滲み出る」 というやつですね。
伝えたい内容を突き詰めて考えたことが、差別化になり、ブランディングになる。 それが顧客認知として受け取られることで、自社のオリジナルが醸成されていくのだと思います。
そして、ブランディングの形成の最中で財産になる一つが、セールスが非常に強くなることです。
その理由が、自社の強みや在り方を考えて出た答えには
- 自信がつく
- 納得がある
- 信念が乗る
- 芯ができる
言葉が走るとというものですね。
そうすると顧客に認知されるためのブランディングは時間をかけて醸成されますが、自社のブランディングを突き詰めて考える過程を踏むことで上記のような状況が作られ、セールスの場で即効性があるものになるのですね。
ブランディングを進めることでの即効性のあるアウトプットについて考えていきたいと思います。